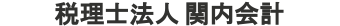2025-02-03
国税庁は、令和7年1月6日、定額減税特設サイト「確定申告に関する情報」を開設し、確定申告における定額減税の適用や確定申告の手続判定フローチャート、所得別に定額減税の詳細について解説が行われている。所得別の定額減税概要は下記のとおりである。
給与所得者
給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整において定額減税を踏まえた所得税額が計算されるため、年末調整を了していれば、確定申告は不要だが、確定申告が必要な場合には確定申告において最終的な定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなる。
年の中途で退職し、給与等に係る源泉徴収について定額減税額の控除が行われていない(控除しきれない額がある場合を含む)ときは、確定申告において定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなる。
公的年金所得者
年金所得者に係る申告不要制度に該当する場合、確定申告は不要だが、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、定額減税額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、確定申告において、最終的な定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなる。
給与と公的年金の両方で定額減税を受けている場合
支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額と、厚生労働大臣等から支払を受けた公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の必要はない。
このため、従来どおり、
・給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている場合、
・その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている場合については、確定申告をする必要はない。
事業所得者等
事業所得者や不動産所得者等は、確定申告の際に所得税の額から定額減税額を控除する。
令和6年分所得税に係る予定納税の対象者は、第1期分予定納税額から本人分に係る定額減税額に相当する金額が控除されていたため、確定申告の際に予定納税額も踏まえて、最終的な年間の所得税額と定額減税額の精算を行う。
源泉徴収票に控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合
給与所得や公的年金所得があり、源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合には、給付金の支給による対応があることがあるが、給付金の詳細については、居住地の市区町村に確認することとなる。
「確定申告書等作成コーナー」による対応
「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、定額減税を適用した申告書も自動計算で作成可能であるが、確定申告書等作成コーナーの画面遷移が昨年までと大きく変わっているため、注意が必要である。
(参考)定額減税と確定申告
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/kakutei.htm#kyuyo