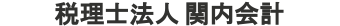2017-10-26
日本法人の海外子会社の主たる事業は「株式の保有」だとして、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たさないとした原処分庁の判断を巡って争われた訴訟の上告審で最高裁第3小法廷(山崎敏允裁判長)は24日、子会社の行っていた地域統括業務には相当の規模と実態があり、株主権の行使や株式の運用に関連する業務等とはいえないと認定、約12億円の課税処分を認めた二審判決を破棄して、処分を取り消した。
タックスヘイブン(租税回避地)税制は、税率が低い国・地域にある子会社の主な事業が「株式の保有」にとどまる場合は日本の親会社の所得に合算して課税する。ただし、子会社が主たる業務を行うに必要と認められる事務所等の固定施設があって、その事業の管理や支配、運営を自ら行っているなど、タックスヘイブン税制の適用除外要件である実態基準や管理支配基準等を満たせば、課税されないこととなっている。
この事件は、原処分庁(刈谷税務署)が、子会社の主たる事業は株式の保有であり、親会社の各事業年度の所得金額の計算上、子会社の課税対象留保金額相当額は益金に算入されるとして、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことが発端。一審の名古屋地裁は親会社の主張を認め追徴課税処分を取り消したが、二審の名古屋高裁は「子会社の主たる業務は株式の保有と認められる」として、原処分庁の処分は適法としていた。
これに対し、最高裁第3小法廷は、子会社の所得金額では保有株式の受取配当の占める割合が8、9割だったものの、地域統括業務中の物流改善業務に関する売上高は収入金額の約85%にのぼっており、子会社が行っていた地域統括業務は、相当の規模と実態を有するものであり、事業活動として大きな比重を占めていたと指摘。タックスヘイブン税制の適用除外要件を全て満たしていることから、課税処分を認めた二審判決を棄却した。
なお、判決においては、租税回避地の子会社が課税対象となるかどうかを左右する「主な事業」の判断基準について、「外国子会社等が複数の事業を営んでいるときは、それぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額、事業活動に要する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定資産の状況等を総合的に勘案して判定するのが相当」との判断を初めて示し注目されている。
最高裁判決は↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/087157_hanrei.pdf