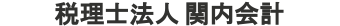2025-03-19
令和7年2月25日、国税庁のインボイス制度特設サイトにおいて、新たな「インボイスの取扱いに関するご質問」が公表された。今回示された内容は、次の4項目となっている。
1. 現金主義を適用する事業者の仕入税額控除のタイミング
いわゆる現金主義の特例の適用を受ける個人事業者については、費用の支出と適格請求書の受領のタイミングが異なり、適格請求書の受領が翌課税期間になることがある。仕入税額控除の適用には、一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書の保存が求められるが、当該課税仕入れが適格請求書発行事業者から行われる場合には、課税期間の終了時までに適格請求書の交付が受けられなかった場合でも、後日、交付された適格請求書を保存することを条件に、仕入税額控除の適用が認められることとなった。
2. 任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき課税仕入れの相手方の氏名又は名称
任意組合が共同事業として課税仕入れを行った場合、幹事会社が仕入先から交付された適格請求書を保存し、構成員は幹事会社からの精算書の保存により、仕入税額控除の適用を受けられることとなっている。この場合、幹事会社が相手方の氏名・名称や登録番号を管理し、必要に応じて構成員が確認できる状態にあるならば、帳簿には幹事会社の名称及び幹事会社を経由して取引を行った旨を記載すれば差し支えないとされた。
3. 任意組合の組合員のうち事業の損益の配賦を受けない者の取扱い
任意組合に関しては、すべての組合員が適格請求書発行事業者として登録し、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出した場合のみ適格請求書の交付が可能となるが、日本で課税資産の譲渡等を行っておらず、日本における事業の損益の配賦を直接又は間接にも受けない組合員については、届出書の対象としなくても差し支えないとされた。
4. 適格請求書の記載事項のインターネットでの公表
適格請求書の記載事項の一部をホームページに掲載しておくだけでは、領収書とホームページの関連が明確でなく、適格請求書の要件を満たしたことにはならない。しかし、取引先に交付する領収書に適格請求書の記載事項である登録番号や名称等が記載されていない場合でも、領収書上に記載されているURLにアクセスすることで不足事項が補完されるのであれば、相互の関連性が明確であるものとして、適格請求書の記載事項を満たしているものと扱われることが示された。
(参考)特集 国税庁 インボイス特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
(参考)インボイスの取扱いに関するご質問(令和7年2月25日更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf